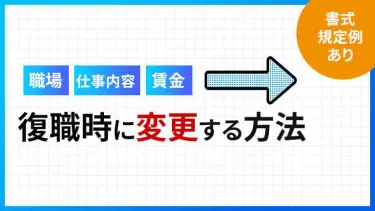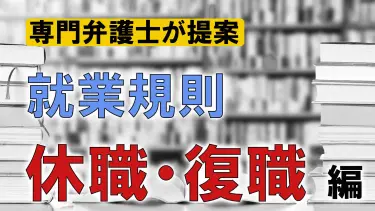現在の業務ができなくとも、他の業務での労務提供を申し出られた場合、これが債務の本旨に従ったものであれば、休職命令を命じても、労働者が賃金請求権を失わない。
合理的な理由があれば、使用者は休職させるか否かの判断にあたり、労働者に受診を命ずることができる。
1 私傷病休職とは
1.1 休職について
休職とは,ある従業員について労務に従事させることが不能又は不適当な事由が生じた場合に,使用者がその従業員に対し,就労を免除すること又は禁止することをいいます。
労働契約は維持されますが、労働義務は一時的に停止し、それに応じて賃金も一部又は全部不支給となります。
休職には、いつくかのタイプがあります。
①労働者の業務外傷病を理由とする傷病休職、②傷病以外の事故による欠勤を理由とする事故欠勤休職,③刑事事件で起訴された者を一定期間または判決確定時まで休職させる起訴休職,④海外留学や公務就任期間中の自己都合休職,⑤出向期間中の出向休職などです。
いずれも各企業の就業規則により自由に設計可能です。
1.2 傷病休職とは
休職のうち傷病休職とは傷病に基づく欠勤が長期間にわたる場合に「休職」処分とし,「休職期間中に休職事由が消滅せず復職しないときは自動退職(当然退職又は解雇)とする」旨定めているタイプの休職です。
休職は実は法律上設置することは義務となっていません。ではなぜ、休職の制度を多くの企業が採用しているのでしょうか。
従業員が自己都合で病気や怪我により仕事が出来なくなった場合、雇用契約上の労務提供義務を果たせないことになります。
回復まで長期間を要するような場合は本来は解雇の対象となります。
しかし、我が国では昭和の高度成長期から続く長期雇用慣行(つまり、採用した後は定年まで同じ企業で勤め上げることをもってよしとする我が国の慣習。国によって違います。)を採用しています。
そして、病気や怪我で仕事ができなくなった場合は、解雇は猶予して、休職という休みをあげて回復を待ちましょう、という発想から傷病休職の制度が作られてきました
これは法律で義務づけられた制度ではなく、各企業にて就業規則において自由に設定・設計できる制度です。
中小零細企業では休職の制度を置いていない会社もあるくらいです。
このように傷病休職は一種の解雇猶予の制度であり(同旨東京地裁H16.3.26独立行政法人N事件),休職期間中は,従業員との労働契約関係を維持しながら労務への従事を免除するものであり,解雇を猶予して傷病の回復を待つことにより労働者を保護する制度であると解されています(札幌地裁H11.9.21北産機工事件)。
2 傷病休職の開始
2.1 就業規則の休職事由に該当する場合
どのような場合に傷病休職が開始されるかは、会社の判断で決めることが出来ます。
就業規則において休職が開始される原因として休職事由を定めておき、休職事由に該当する場合に傷病休職が開始されます。
例えば、以下のような就業規則の休職事由に該当する場合に、会社が休職を命ずることになります。
第●条(休職)
従業員が、次の各号のいずれかに該当するときは、会社は休職を命ずることがある。
(1) 業務外の傷病により欠勤が、継続又は断続を問わず日常業務に支障をきたす程度に続く(概ね欠勤日から30日程度を目安とする。)と認められるとき。
(2) 精神又は身体上の疾患により通常の労務提供ができず、その回復に一定の期間を要するとき。
・・・・・・・・以下省略・・・・・
2.2 休職開始のポイント
主治医の診断に基づいて決定する
傷病休職の場合、休職事由に該当するか否かの判断は会社が行います。
もっとも、会社の判断の前提として、医師(特に主治医)の診断内容が重要な情報となります。
そこで、就業規則には主治医の診断書の提出義務や、必要に応じて会社が主治医と面談して事情聴取をすることができるような定めを置いておくべきでしょう。
欠勤の前置きは必須条件ではない
休職事由として「業務外傷病により、欠勤が引き続き3か月以上に及ぶとき」といった定めを置く企業も多くあります。しかし、これでは休職発令の前提として3ヶ月の傷病欠勤が必要となります。
しかし、一定期間の欠勤の前置きはなくとも、傷病による欠勤がある程度の期間見込まれる場合は休職を提供してもよい場合も多くあります。
休職制度は前記のとおり傷病による労働者の労務不提供が不能又は不完全な場合の解雇猶予措置です。一定期間の欠勤という前提事実がなくとも、傷病による労働者の労務不提供が不能又は不完全という状況がある場合は休職を命じてもよいと考えられます。
そこで、上記規定例のように欠勤の前置きを必須としない休職事由を定めるとよいでしょう。
休職命令書を発行する
休職を開始する場合は、休職事由に該当すること、休職期間、休職中の遵守事項、休職期間満了前に復職出来ない場合は退職となること等を明記した文書を従業員に交付します。
3 休職中の法律関係
3.1 休職期間
休職期間の長さ等は会社が就業規則で自由に設計可能です。
ポイントは以下のとおりです。
① 休職制度の対象者は、正社員に限り、勤続1年未満は対象外とする
上述のとおり休職制度は長期雇用慣行の産物です。長期間働いてくれることの恩典なのです。それゆえ、長期雇用を前提とした正社員(無期)で、かつ、最低でも1年以上の勤続年数を超えている者に限定することがよくあります。もちろん、正社員限定なし、勤続期間なしでも問題ありません。
② 休職期間は、勤続年数に応じて設定する
同じく長期雇用慣行との関係で、休職期間を勤続年数に比例して定めることが多くあります。こちらも自由設計可能ですので、一律でも問題ありません。
③ 通算規定を定める
従業員によっては、休職期間満了間近にかかりつけの医師の診断書を提出して復職したが、1~2か月後に再び病気欠勤となり、再度休職となるケースがあります。制度を悪用していると思われる場合もあります。
そこで、「6か月以内に同一又は類似の傷病で欠勤するときは、復職前の休職期間の残存期間を休職期間とする」といった規定を入れます。
3.2 休職中の賃金支払義務
休職期間中は無給が原則
休職期間中の賃金を支払うか否かは自由に設計可能です。
一般的には休職期間は賃金を払いません(無給)。
もちろん全額支払う、一定期間だけ支払う、一部手当だけ支払うなどと定めることも可能です。
傷病手当金の受給
業務外の負傷または傷病による療養のため労務に服することができない場合、休業4日目以降については、健康保険法に基づき傷病手当金が支給されます(同法99条1項)。
支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2です。その支給は、同一の負傷または疾病について、1年6カ月が限度とされています(同条2項)。
傷病手当金の受給ができる場合はその手続を従業員に教示します。
3.3 休職中の療養専念義務
傷病休職期間は、業務外の負傷または疾病の療養のために認められた就労免除期間ですから、休職者は療養に専念する義務を負っています。
就業規則や休職発令書にも休職期間中は療養に専念するように記載することがあります。
もっとも、療養専念義務があるとしても、休職期間中は自宅や病院に引きこもっていないといけないという訳ではありません。
特にメンタルヘルス不調者は、気分転換に外出をしたり、スポーツをしたり、ときには旅行をしたりする者もいます。それを知った経営者や同僚従業員が不満を持つことも希ではありません。
しかし、このような行動はこのような行動があったとしても、休職の前提となった傷病と矛盾しているとは言い切れませんので、直ちに休職を取り消すということはできません。
療養に「専念する」とは、四六時中治療を受けているとか、静養しているということを意味するものではなく、社会通念上、それ以外の行為をすることもある程度許
容されていると見るべきです。
4 休職の終了
休職は,休職期間が終了し,または休職事由が消滅することによって終了します。
この場合,休職事由が存続しているか消滅しているかによって,労働者は復職または自動退職・解雇となるので,休職事由の存否が問題となります。
4.1 休職事由の消滅と復職手続
休職事由が消滅した場合,復職は自動的に行われるのか,それとも使用者の発令を必要とするかは、就業規則の定めによります。
休職事由の消滅によって当然復職という定めをしていれば、休職事由の消滅を労働者が証明した場合は当然に復職となります。
これに対し、復職に使用者の意思表示を要する制度の場合(「休職事由が消滅したときは,従業員の復職願いにより復職を命ずることがある」等の規定)は,使用者の発令が必要となります。
もっとも、後者の場合であっても、休職事由が客観的に消滅しているにもかかわらず、使用者が正当な理由なく復職を発令しない退職扱いとすることは,就業規則違反として無効となります(JR東海[退職]事件・大阪地判平成11・10・4労判771号25頁)。
その場合、復職拒否後の賃金支払義務が認められます(民法536条2項 ヴィテックプロダクト事件・名古屋高判平成26・9・25労判1104号14頁)。
4.2 傷病休職における「治癒」とは?
傷病休職の場合,休職事由となった傷病が治癒したことが、休職事由の消滅自由となります。
もっとも、労働者がどの程度の健康状態に回復すれば,傷病の治癒によって復職が可能となったといえるかが問題となります。
この点、原則として,治癒と認められるためには、労働者が原職(休職以前に従事していた職務)を支障なく遂行できる健康状態に復したことを要すると解されます(平仙レース事件・浦和地判昭和40・12・16労民16巻6号1113頁、アメックス事件・東京地判平成26・11・26労判1112号47頁)。
また、治癒についての主張・立証責任は労働者側が負います。
もっとも、休職期間満了時点において、完全に治癒していない場合であっても、相当の短期間内の原職復帰が可能であり,軽度の職務に就労させることが可能であ
れば,信義則上,当該職務に配置するよう配慮する義務を負うと解されます(ェール・フランス事件・東京地判昭和59・1・27労判423号23頁)。
つまり、休職期間満了時点で100%であることが原則ですが、その時点で100%でなくとも、短期間軽い職務についてもらえば100%となることが確実である場合は、休職期間満了でバッサリ退職とすることには慎重になる必要があります。
なお、復職当初は、従前より軽度な業務に就かせ、業務の変更・減縮に伴い、労働時間を縮小し、賃金を減額する場合は、その旨の就業規則上の根拠規定を置くと共に、合意文書を取り交わすことが適当です。
4.3 休職期間満了による退職・解雇
復職事由が認められない場合,労働者は休職期間満了によって解雇または自然退職となります。
このうち自然退職は,労働契約の一種の自然終了事由を意味し,解雇ではありませんので,権利濫用法理の規制に服しません。
もっとも、その代わり,休職自体について相当性の要件が課されます。
これに対し,休職期間満了を待って使用者が改めて解雇を行う就業規則の定めとなっている場合は、解雇は解雇権濫用規制(労契16条)に服します。
傷病休職の場合は,解雇回避措置として、軽度の職務への配置義務が要件となり,そうした配置の可能性があるにもかかわらず,それを怠ったまま行われた解雇は無効となる可能性があります。