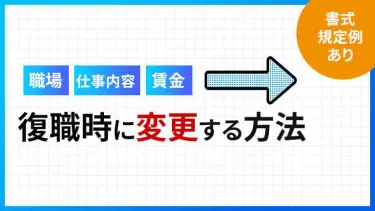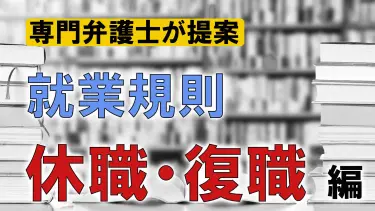1 傷病による欠勤は解雇事由になる
従業員が傷病によって雇用契約の本旨に従った労務提供が全くできなくなった場合(履行不能)や一部しかできなくなった場合(不完全履行)は,契約上の債務が不履行となっていますので,これらは原則として普通解雇事由に該当します。
多くの会社の就業規則では,「身体の障害により業務に堪えられないとき」を普通解雇事由として定めています。
2 傷病休職制度がある場合はすぐには解雇できない
しかし、現在多くの企業では,私傷病の場合の休職制度を導入しています。
私傷病休職制度は,私傷病で欠勤ないし不完全な労務提供が2~3カ月間続いた場合に,就業規則の規定に基づいて,勤続年数に応じた一定期間の休職期間を与え,休職期間満了時に治癒していれば復職を認め,治癒していなければ労働契約を解消するというシステムです。
解雇を一定期間猶予する機能を有します。
そして,就業規則により休職制度を導入しており,かつ,休職制度の適用条件を満たす場合は,原則として所定の期間休職させて回復の機会を与えることが必要です。
休職を経ない解雇は,解雇回避措置をとらない不相当な処分として解雇権の濫用(労働契約法16条)、つまり解雇無効となる可能性が高いと言えます。よって,私傷病休職制度がある場合は同制度の適用を検討する必要があります。
3 休職を繰り返す場合
3.1 休職期間が残っている場合
休職を繰り返したとしても、会社の就業規則上の休職期間が残っている場合は、その期間の満了を待たずに解雇をすることは、無効となる可能性が高いです。
例外として、残存休職期間を適用しても回復の見込みがない場合には、残存休職期間を適用せずに解雇しても解雇権濫用とならずに有効となると考えられます。
3.2 休職期間が残っていない場合
この場合は、休職を適用せずに、解雇を検討することが可能です。
傷病を理由に欠勤が続き、その後も回復が困難で、雇用契約の本旨に従った労務提供が全くできなくなった場合(履行不能)や一部しかできなくなったといえる場合は、普通解雇事由に該当し、解雇を行うこともできます。
ただし、解雇が有効となるためには、医者の診断や意見を踏まえ、かつ、職種・職務を限定せずに雇用されている場合は職種変更や配置転換も検討する必要があります。詳細は下記記事をご参照ください。
社長当社の従業員Aは,職種・職務を限定せずに採用したのですが、持病の椎間板ヘルニア等の疾病のため,欠勤している者がいます。欠勤前から元々,立ったり座ったりと腰に負担のかかる業務を担当していたため,原職に復帰できる見込みはあり[…]
4 休職を繰り返し使われることを予防すべし
4.1 通算規定
従業員によっては、休職期間満了間近にかかりつけの医師の診断書を提出して復職したが、1~2か月後に再び病気欠勤となり、再度休職となるケースがあります。制度を悪用していると思われる場合もあります。
そこで、「6か月以内に同一又は類似の傷病で欠勤するときは、復職前の休職期間の残存期間を休職期間とする」といった休職期間の通算規定を入れて予防できるようにしてください。
4.2 通算規定の導入の不利益変更該当性
もっとも、再休職制度(休職期間の通算あり)を創設する就業規則の変更は、労働条件の不利益変更に当たるといえます。
したがって、原則として、労働者の同意がない限り、その効力を生じません(労契法9条本文)。
しかし、変更の必要性が存し、変更内容に相当性が認められ、その他の事情をも総合して当該変更が合理的であるといえるならば、当該変更の同意が得られない場合であっても、効力を有することになります(同条ただし書き・10条本文)。
再休職制度(休職期間の通算あり)は、一般的に変更の必要性が認められる余地があり、一定の要件を備えた内容であれば、変更内容の相当性も肯定され得るといえます。よって、合理性を有する変更として効力を有すると評価される可能性も十分あります。
例えば、(1) 復職後に従前の休職事由となった疾病と「同一ないし類似の疾病」によって欠勤し始めた場合を対象にするという限定をつける、(2) 再休職発令の要件を限定する(単に1日欠勤しただけでなく、客観的に労務提供が困難な状況を要求する。)、(3) 欠勤によって休職が通算されるようになる期間を限定する(例えば、6ヶ月~1年程度)、(4) 通算後の休職期間を0にしない(30日とする例が多いが、それ以下でもよいと考える。)。などです。
これに対して、私は、休職期間満了退職は解雇ではありませんし、再休職の場合は、前提として前回30日以上の休職期間を付与されているはずですので、必ずしも30日とする必要はないと考えます。