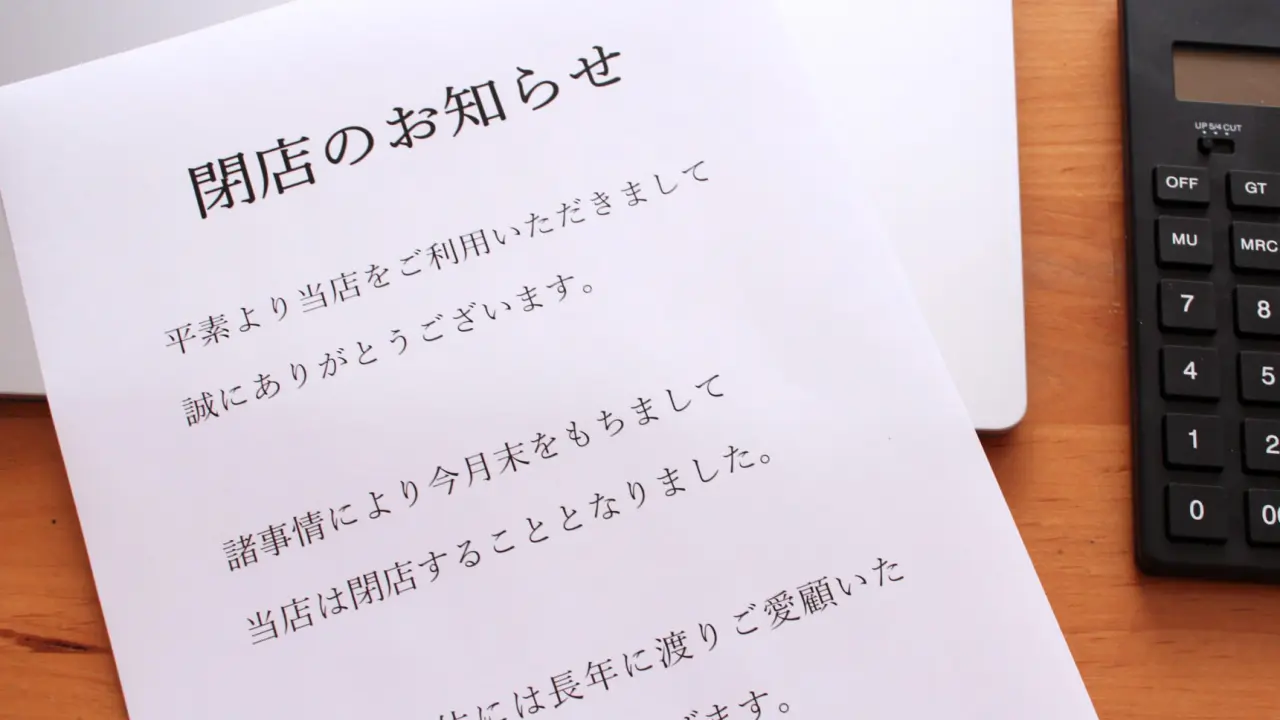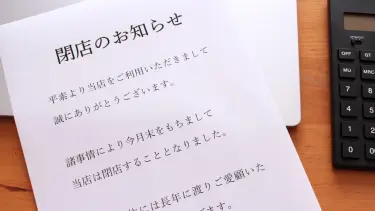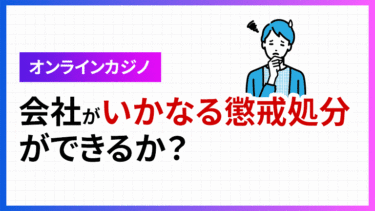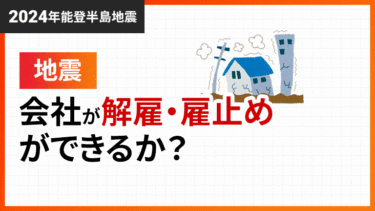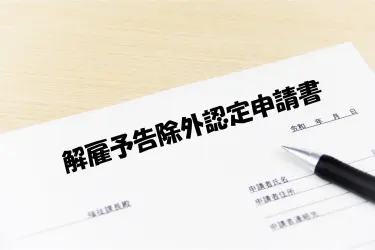会社解散による解雇の有効性
偽装解散の場合の解雇の有効性
実務上の注意点
1 会社解散とは
1.1 解散とは
解散とは、会社の法人格の消滅を生じさせる原因となる事実をいいます。
- 株式会社は以下の事由によって解散します(会社法471条・472条)
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散の事由の発生
- 株主総会の決議
- 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
- 破産手続開始の決定
- 株式会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき等(会社824条1 項)、株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき等(会社833条1 項)において解散を命ずる裁判があったとき
- 休眠会社のみなし解散(休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したものをいう)は、法務大臣が休眠会社に対し2 か月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その2 か月の期間の満了の時に、解散したものとみなされる(会社472条))
解散すると、合併の場合は法人格が消滅し、破産の場合は破産手続が開始され、それ以外は清算手続が開始されます。
清算手続中において、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があるか、債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態)の疑いがあるときは、清算人等
の申立てにより特別清算が開始され、破産手続と同様厳格な整理が行われることになります。
破産手続、清算手続、特別清算手続、いずれも、解散に続いて会社の後始末を行う手続で、株式会社の法人格は、破産手続又は清算手続終了時に消滅します。
本記事では、株式会社が株主総会の決議によって解散し、清算手続を経て会社が消滅する場合について解説します。
1.2 解散・清算の流れ
手続の具体的な流れは以下のようなものになります。
- 株主総会の招集
総会の2週間前に取締役会決議により株主総会の招集通知を発送します。 - 株主総会の特別決議
株主総会での解散の決議は、特別決議の要件で行う必要があります。
一般的には、この解散の決議と同時に、清算人の選任を行います。
清算人とは、会社解散後の清算事務を行う人で、多くの場合、代表取締役がそのまま横滑りで清算人に選任されます。 - 解散・清算人選任の登記
解散の日から2週間以内に、法務局で解散と清算人選任の登記申請を行う必要があります。 - 各種機関へ解散の届出
会社解散の登記完了後すみやかに各種機関へ解散の届出をしておく必要があります。届出先は、市区町村役場、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、社会保険事務所などです。 - 財産目録・貸借対照表の作成
就任した清算人は遅滞なく、会社の財産を調査し、財産目録と貸借対照表を作成する必要があります。作成した財産目録と貸借対照表は、株主総会の承認を得て会社に保管しておきます。 - 債権者保護手続き
清算人は、会社の債権者に対して会社の解散を知らせ、2ヶ月間以上の一定期間内に債権を申し出るべき旨の官報公告と会社が認識している債権者に対して催告を行います。 - 解散確定申告書を提出
解散日から2ヶ月以内に、事業年度開始日から解散日までの確定申告を税務署にて行います。 - 現務の結了、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の分配等の清算事務
清算人は、売掛金等の会社の債権を回収し、買掛金や借入金など会社の債務を支払います。また、現務の結了として、従業員の任意退職や解雇を行います。全ての債務を支払ってもまだ財産が残る場合は、株主に分配し清算します。その上で、清算人は残余財産確定日を決定します。 - 清算確定申告書を提出
残余財産の確定後、1ヶ月以内に税務署に清算確定申告を行い、所得があれば納税します。 - 決算報告書の作成・承認
清算人は清算事務が終了すれば遅滞なく決算報告書を作成し、株主総会を開催して清算事務報告の承認を受けます。この承認により、会社の法人格が消滅することになります。 - 清算結了の登記
株主総会で清算事務報告の承認を受けてから2週間以内に、清算結了の登記申請を行います。 - 税務署等へ清算結了の届出
清算結了の登記完了後すみやかに税務署、都道府県税事務所、市区町村役場などに清算結了の届出を行います。
1.3 解散と雇用関係
使用者が法人であって、その法人が解散する場合には、清算手続が完了すれば法人格は消滅し、労働契約関係も消滅します。
株式会社においては、会社が解散し、清算手続に入ると、清算の目的の範囲内で清算が結了するまで存続します(会社法476条)。
清算手続中の会社は清算株式会社と呼ばれ、以下のような状態となります。
① 営業行為不可
清算株式会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなされるだけであるから(会社476条)、清算事務の遂行に必要な範囲内でのみ営業
(在庫商品の売却等) を継続する外は、営業取引をすることはできなくなります。
② 取締役・代表取締役は退任し、清算人が就任する。
清算株式会社は、営業を行わないため取締役、会計参与、会計監査人は地位を喪失し、清算事務は清算人が行うことになります。
清算株式会社の必要的設置機関は、株主総会と清算人であり、定款の定めにより清算人会、監査役、監査役会を設けることができます(会社477条2 項)。
清算人は、現務の結了、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の分配等の清算事務を行いいます(会社481条)。
清算株式会社には、1 人又は2 人以上の清算人を置かなければなりませんが(会社477条1項)、定款で定めてある場合又は株主総会において他の者を清算人に選任した場合を除き、取締役全員(ただし委員会等設置会社の場合には監査委員以外の取締役)が清算人になります(会社478条1 項・5 項、法定清算人)。
会社の代表取締役や取締役であった者以外の者を株主総会で清算人に選任することも可能です。
③ 労働契約関係
清算人は、従業員との労働契約について、退職金等を支払いつつ、任意退職ないし解雇を実施することとなります。
従って、遅くとも清算の終了時には雇用契約関係も消滅します。
2 会社解散による解雇の有効性
2.1 会社解散の解雇の有効要件
会社解散による解雇の場合といえども、解雇の一般的有効要件を満たす必要があります。
つまり、労基法の解雇予告義務(20条)や労働協約上の解雇協議義務などの適用があります。
普通解雇の有効要件については
また、雇権濫用規制(労契16条) も雇用関係の一般的ルールとして適用されます。
もっとも、解散による企業廃止を理由とした普通解雇は、通常は、「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当として是認できる場合」にあたると考えられます。
また、会社解散による解雇は、企業が存続することを前提に、人員削減措置をとる整理解雇とは異なりますので、いわゆる整理解雇の法理は適用されません。
しかし、①手続的配盧を著しく欠いたまま解雇が行われたものと評価される場合や、②解雇の原因となった解散が仮装されたもの又は既存の従業員を排除するなど不当な目的でなされたものと評価される場合に、解雇権の濫用として無効となります。
2.2 手続的配慮とは
解散による解雇が社会通念上相当であるためには、解散のいきさつ、解雇せざるをえない事情、解雇の条件などは従業員に対し説明するなどの手続的な配慮が求められます。
このような手続的配慮を著しく欠いたまま解雇が行われたという場合には、「社会通念上相当として是認」できない解雇として、例外的に解雇権が無効となる場合があるので注意が必要です(グリン製菓事件一大阪地決平10. 7. 7労判747号50頁、三陸ハーネス事件一仙台地決平17.12.15労判915号152頁)。
他方で、急激な業績悪化に伴い解雇を行った際、短期間(1~2ヶ月)でも団体交渉に応じて説明を行い、僅かでも解決金を提示して合意退職を図った場合は、手続的配慮は問題なく解雇は有効と判断されています。
会社解散・清算を前提とした解雇が,整理解雇法理による有効性判断は採用せず、解雇は合理的で有効とされた例
2.2 労働組合を嫌悪して会社を解散させた場合
解散による事業の廃止が、労働組合を嫌悪し壊滅させるために行われた場合には、解雇が無効となる場合があります。
例えば、従業員が労働組合に加入し、団体交渉で賃金増額や残業代を求めてきたことを受け、経営者がこれを嫌い、会社を解散させることで対抗するような場合です。
この場合、会社解散それ自体は有効であるとしても、清算会社による解雇は労働組合法の強行法規(労組7条1号)に違反するものとして無効となる場合があります。
清算会社による解雇が無効となった場合は、清算会社に対する労働契約上の地位の確認や賃金請求が認められ場合があります。
賃金請求が発生し続ける場合は、いつまでたっても会社の清算が結了しない(法人が消滅しない)ことになります。
では、どのような場合に不当労働行為として清算会社の解雇が無効となるのでしょうか。
基本的には、組合嫌悪を決定的な動機として会社解散及び解雇がなされたといえるか否かが問題となりますが、以下の①~④の要素を総合考慮して判断されます。
①経営不振の程度
経営不振の程度が、企業の継続が不可能な程までに深刻なものであれば、業績不振が決定的動機で解散をしたとの推定が強くなります。
これに対し、業績不振ではあるものの事業継続が合理的に可能である場合、例えば、合理的な資金調達、経費削減等の合理化等により企業の継続はなお可能である場合などは、組合嫌悪が理由で解散されたとの推定が働きます。
②反組合的言動や他の不当労働行為の存否
使用者に、普段から反組合的言動(「労働組合なんかに加入して、会社を畳んでやる」等)があったり、支配介入・団体交渉拒否等他の不当労働行為があると、組合嫌悪を決定的動機とするものであったとの推定が強くなる。
③組合活動と解散の時期関係
解散が、組合結成や組合活動の活発化等に呼応するような時期になされていれば、組合嫌悪を決定的動機とするものであったとの推定が強くなる
組合設立から数ヶ月で解散を決定した場合は、組合嫌悪を理由として解散・解雇をしたと推定されます。
これに対し、経営不振が続いており、組合が介入する前から会社の事業廃止を検討していた場合は、組合嫌悪を決定的理由として解散したとは推定されにくくなります。
④企業継続の存否
解散後も企業が別の法主体の下で継続していれば、組合嫌悪を決定的動機とするものであったとの推定が強くなる。
これに対して、解散する会社の事業は完全に終了して誰にも引き継がれない場合は、組合嫌悪を決定的理由に解散されたとは推定されにくくなります。
3 偽装解散による解雇
偽装解散とは
解散会社が事業の廃止を装いつつ、何らかの形で事実上事業を継続している場合があります。
例えば、
- 実際には株主総会の解散決議といった解散手続がとられていないのに会社を解散すると称して従業員を解雇し、経営者は会社を継続する場合
- 組合排除の動機ないし目的を持ちつつ会社が解散され,解散後に別会社が新設され,ほとんどの従業員はその新会社に採用されるも,一部の従業員(組合員など)のみ採用されなかった場合
などです。このような形態は、解散を偽装していることから、偽装解散と呼ばれています。
偽装解散の場合は、整理解雇の法理が適用され、解散による事業廃止を理由とする解雇は「客観的に合理的な理由」を欠き無効とされえます。
偽装解散は、上記2.2と同様に経営者が組合を嫌悪して労働組合壊滅の目的で行われるものが多く、不当労働行為も問題となることがあります(2.2の場合は、事業を完全に廃業する場合です。これに対して、2.3の場合は、事業は別の形で存続する場合です。)。
偽装解散における問題の所在
偽装解散の場合であっても、上記①のように、経営主体に変更がない場合は、解雇が無効となり、もともとの使用者に対して地位確認や賃金請求が行われることになります(ジップベイツ事件 名古屋高判平16.10.28労判886-38)。
これに対して、上記②の組合排除の動機ないし目的を持ちつつ会社が解散され,解散後に別会社が新設され,ほとんどの従業員はその新会社に採用されるも,一部の従業員(組合員など)のみ採用されなかった場合は労働契約の承継の有無が問題となります。
この場合に、形式的には、別会社との間で新たな労働契約が締結されれば雇用は継続し、締結されなければ雇用は継続しないことになります。
解散会社から事業譲渡を受けたとしても、別会社には採用の自由がありますので、採否を自由に決定できるのが原則です。
解散会社にいた労働組合員を採用しないことも自由なはずです。
しかし、偽装解散は、労働組合排除のために計画的に行われているので、上記のような形式論を乗り越えて、労働者が事業を譲り受けた別会社との間で雇用関係が認められないかが問題となります。
① 別会社との間で雇用関係の継続が認められない場合
労働者の雇用関係の継続が否定される結論も少なくありません(静岡フジカラーほか2社事件 東京高判平17.4.27 労判896-19、東京日新学園事件 東京高判平17.7.13 労判899-19など)。
その他、事業継続が極めて困難な見通しの中で解散に伴う従業員の解雇が行われた後,従業員の雇用先確保を目的に新会社が設立された事案で,取引先も営業活動も従業員もほぼ同一でしたが,株主構成・役員構成が異なり,新旧会社間で会社財産・経理・業務などで混同もみられないことから,新旧会社に同一性はなく解散が偽装であったとは認めがたいとして,解散に伴う解雇を有効と判断する裁判例があります(東北造船事件 仙台地決昭63.7.1労判526-38)。
これらは別会社の採用の自由に基づく原則論を認めた例になります。
これに対し、以下の②~④は裁判例による雇用契約の継続を認めるロジックとなります。
② 解散会社(譲渡会社)と別会社(譲受会社)の実質的同一性
解散会社と、その事業を継続する別会社の間に、資本関係、資産内容、経営陣、業務内容等の点で実質的同一性が認められることを理由として、解散会社の労働者の別会社への承継を認めたり、別会社が解散会社の労働者を不採用とすることに対して解雇法理の適用を認めたりするものがあります。
「実質的同一性」のメルクマールとして,譲渡企業と譲受企業の事業内容,資本,役員構成,設備,営業所の継続の有無,雇用契約関係承継の規模,退職金の支払の有無などを掲げ,これらを総合考慮して実質的同一性を決定しています(新関西通信システムズ事件 大阪地決平6.8.5 労判668-48、日進工機事件 奈良地決平11.1.11 労判753-15など)。
③ 解散会社と別会社間の労働契約承継の合意の認定
解散会社における労働契約を別会社に承継させる旨の両会社間の合意の存在を認定し、事業譲渡に関する法理に基づく別会社への労働契約承継を認める裁判例があります。
タジマヤ事件(大阪地判平11.12.8 労判777-25)では、譲渡企業と譲受企業の実質的同一性が認められない場合であっても,「(譲渡会社に在籍した他の)従業員全員を雇用していることからすると,譲渡の対象となる営業には,これら従業員との雇用契約を含むものとして営業譲渡がなされたことを推認できる」として雇用関係の承継が認められました。
勝英自動車学校(大船自動車興業事件 東京高判平17.5.31 労判898-16等)では、解散は偽装解散ではなく真正解散であり,解散を理由とする解雇は,「特段の事情のない限り」有効であるとしました。もっとも、全従業員の労働契約を承継する原則的合意と例外的に労働条件変更を拒否した従業員を承継から排除する合意を認定した上で、後者を公序良俗違反により無効とし、前者に基づいて、労働条件の変更を拒否した従業員の雇用の承継を認めました。
④ 法人格否認の法理
最後は、法人格否認法理によって解散会社が事業を継続した別会社と別個独立の法人格であることを否定し、別会社での雇用継続という帰結を導くものです。
会社解散及び事業譲渡をなした目的が,整理解雇を回避するためにあり,しかも譲渡企業と譲受企業が実質的同一性を有するなど,譲受企業の「法人格が法律の適用を回避するために濫用されている場合」には,法人格否認の法理により譲受企業に雇用契約の承継が認められることもあります。
裁判例では,Z研究所及びその著作権管理や教材の出版部門を独立させ設立されたY1社並びに同研究所の新開発行部門が独立して設立されたY2社は,いずれもZ研究所の代表者及びその一族が経営する同族企業であり,本店所在地は同一であり,事業目的も共通性があり,財政的にもZ研究所に依存しており,取締役会,株主総会のいずれも開催されたことはなく,組織の改編や経営方針,経理,人事異動等,企業活動のほぼ全面にわたりZ研究所の代表者が決定し,Z研究所と研究所の代表者とは,財産の混同もみられるところであるところ,Z研究所に雇用されていた労働者Ⅹが,Z研究所が事実上倒産したため,Z研究所の事業を引き継いだYl1に対し,地位確認を求めるとともにY2社に対し不法行為による慰謝料を求めた事案について,Z研究所の代表者は,Z研究所及びYl社及びY2社を自己の意のままに管理支配できる地位にあったとし,Z研究所は,全国各地で倒産直前に貸金不払いを累積させている一方、倒産直前にY1社及びY2社に対する多額の業務委託費を支払ったり,倒産直後には受講生及び顧客データをY1社及びY2社に無償で譲渡していることなどからみると「原告その他の債権者に対して負担する多額の未払い賃金等の債務を免れる目的で,営業権の全てを被告2社に承継させ,自らを倒産させたものと認めるのが相当である。したがって,Z研究所の倒産及び被告2社への営業権の承継は,原告その他の債権者に対するZ研究所の債務の免脱を目的としてされた会社制度の濫用というべきである」として,法人格の否認の法理によりYl社に対する雇用関係の確認を認めています(日本言語研究所他事件・東京地判平12・12・10・労判1000.35)。
4 実務上の注意点(まとめ)
会社解散に伴う解雇を行う場合の対応について、以下のとおりまとめます。
- 会社の業績が悪化し、事業を廃止することは、経営者が自由に決定できます。赤字企業を継続して会社の資産が枯渇する前に会社を閉じるという判断は尊重されます。
- 廃業する際は、会社の解散手続を行い、解散の前後において、従業員との雇用契約を終了させることになる。
- 雇用契約終了に際しては、会社を廃業する理由等について従業員に説明し、いきなり解雇することはできるだけ避ける(ただし、急激な業績悪化により時間的余裕がない場合はその限りではない)。特に労働組合が存在する場合は、早めに説明する(出来ればそれ以前の団体交渉においても、会社の経営状況が悪化しており事業の継続が難しいことを説明しておく。)。
- 僅かでも退職一時金のようなものを提案して、合意退職を目指す。それでも退職に応じない場合は、会社解散を理由に解雇をする。解雇の場合は解雇予告手続等はしっかりと行う。
- 会社は解散するが、事業は継続する場合は、偽装解散等と言われないように注意する。具体的には、資本関係、資産内容、経営陣、業務内容等が別の会社に事業譲渡するように注意する。
以上になります。
お分かり頂けましたでしょうか。ご参考にしていただければ幸いです。