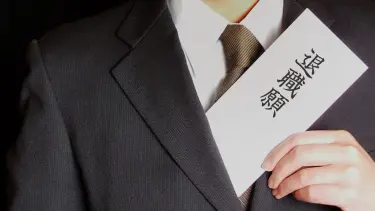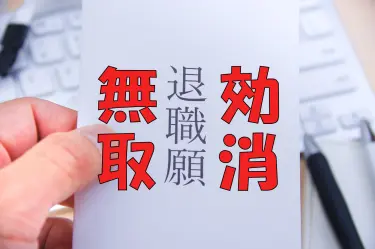就業規則などで辞職を1ヶ月以上前に出すことを義務づけたり、会社の承諾がないと退職できないと定めることが許されるか
有期雇用契約で期間途中で退職することができる場合
法律で許されないタイミングで退職した場合に損害賠償責任が発生するか
1 辞職について法律が定めるルール
1.1 雇用期間の定めのない場合
2週間の予告期間をおけば、労働者は一方的に労働契約を解約することができます(民法627条1項)。この場合、労働契約の解約の申し入れがなされた日(初日不算入 民法)から2週間が経過すれば雇用契約は終了することになります。
辞職とは、労働者による労働契約の解約(退職)を意味します。辞職はあくまでも労働者の一方的な意思表示によって効力が生じ、使用者の承諾は必要ありません。似て非なる概念として労働契約の合意解約があります。労働契約の合意解約とは,労働者と使用者が労働契約を将来に向けて合意により解約することをいいます。労働者が合意解約を申し込んで使用者が承諾する場合を依願退職といいます。この記事は辞職に関しての記事ですのでご注意ください。
民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
1.2 雇用期間の定めのある場合(有期雇用契約)
原則として期間途中の辞職は認められない
労働者は「やむを得ない事由」がある場合でなければ、期間途中で辞職することはできません。
また、やむを得ない事由がある場合でも、それが労働者の過失によって生じたもので、使用者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する義務を負います(民法628条)。
民法628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
1年を超える期間の有期契約でも1年経過後は辞職できる
ただし、1年を超える期間の定めのある雇用契約を締結した場合、契約期間の初日から1年を経過した後は、いつでも自由に辞職することができることが暫定的に認められています(労基法附則137条 ただし、この場合でも、民法627条1項により2週間の予告期間が必要です)。
例えば、期間3年の雇用契約をしていた場合であっても、契約期間の初日から1年を経過した後は、2週間の予告期間を置けばいつでも辞職できます。
もっとも、期間1年の有期契約を更新した場合、2年目の契約期間の途中に辞職することはできません。
労基法附則137条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
この規定は、従来有期雇用契約の最長期間は1年(例外3年)とされていましたが、2003年の法改正により契約期間の上限が3年(例外5年)に延長されたことを受けて暫定的に定められました。もっとも、この労基法の定めは、①一定の事業の完了に必要な期間を定めた場合、②専門的知識等を有する労働者および③60歳以上の労働者との有期労働契約には適用されません。
① 一定の事業の完了に必要な期間を定めた場合
例えば4年間で完了する土木工事において、技師を4年間の契約で雇い入れる場合のように、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要です。
② 専門的知識等を有する労働者
次に掲げるいずれかの資格を有する者
① 公認会計士
② 医師
③ 歯科医師
④ 獣医師
⑤ 弁護士
⑥一級建築士
⑦ 税理士
⑧ 薬剤師
⑨ 社会保険労務士
⑲ 不動産鑑定士
⑫ 技術士
⑫ 弁理士
この場合、労働者が①〜⑫の国家資格を有していることだけでは足りず、当該国家資格の名称を用いて当該国家資格に係る業務を行うことが労働契約上認められている等が必要です(平15.10.23基発1022001号)
その他、博士の学位を有する者、情報処理の専門資格を有する者、特許に関する専門的知見を有する者など
③ 60歳以上の労働者
契約締結時に満60歳以上である労働者との労働契約
2 民法627条の予告期間を超えて辞職を引き延ばすことはできない
2週間の予告期間を置けばいつでも辞職できるとしても、会社としては、2週間で代替の人材を採用することは現実的には困難です。また、2週間では十分な引き継ぎもできずに業務に支障が生ずることもまれではありません。
そこで、急な退職への対抗策として、「退職を希望する場合は遅くとも1カ月前に退職願を提出しなければならない」もしくは「会社の承認を得なければならない」などの定めを就業規則に定めている会社もみられます。また,このような定めが無くとも,退職者からの退職の申し出を拒絶し、事実上退職の時期を引き延ばそうとすることがあります。
しかし,民法627条は労働者の退職の自由(職業選択の自由 憲法22条1項)を保障する趣旨の(片面的)強行規定であり,これに反する就業規則等の規定や処理は無効となると解されています(土田道夫「労働契約法[2版]」632頁~有斐閣)。よって,民法627条について労働者に不利になる態様での辞職の予告期間を延長することは出来ないと解されます(※1反対説もあり)。
よって,「退職を希望する場合は遅くとも1カ月前に退職願を提出しなければならない」もしくは「会社の承認を得なければならない」などの定めがあり退職を拒絶したとしても,上記1の民法627条の予告期間を置けば辞職の効力は生ずることになります。
「民法の規定は,任意法規と解するのが一般的であり,労働契約や就業規則のうえで民法の規定と異なる定めをしておけば、その定めによることになり、右の「二週間」を特約により延長することも可能(厚生労働省監修『改定版・新労働法実務相談』95頁)とし、これが極端に長い場合には、労働者の退職の自由が極度に制限されることとなり、民法第90条により無効となるが、労基法第20条とのバランスから一カ月までならば適法とする見解(下井隆史『労働基準法・第四版』 201頁)もある」(安西愈「採用から退職までの法律知識[13訂版]」916頁~中央経済社)。
3 労働者が希望し会社が了承する場合は退職までの期間を短縮できる
労働者が民法627条の予告期間を置かずに退職することを希望し,使用者もそれを了承する場合は,退職の時期を短縮することが出来ます。
例えば,労働者が即日退職を希望した場合,会社が了承するのであれば即日退職の効果が発生します。
4 辞職した社員への対抗策
辞職が法的に認められる場合
辞職が法的に認められない場合
5 対応方法
事実関係及び証拠の確認
まずは,以下の事実及び証拠を確認する必要があります。
労働者の退職の意思表示
【証拠】
□ 退職届・退職願
□ メール
□ 口頭(録音,記録)
雇用契約の内容
【証拠】
□ 雇用契約書
□ 就業規則,賃金規程
労働者の退職時期に関する意思
【証拠】
□ 人事・上司の報告書
説得活動
突然の退職に対しては,最終的には上記のとおり法律の定めに沿った対応をせざるを得ませんが,説得することは可能です。退職時期について労働者を説得し,引き継ぎ等を十分なし得る時期での退職の同意を得るように努力します。
労働者との交渉
会社が労働者の退職を拒絶した場合,労働者は退職処理をするよう求めてきます。また,退職妨害をしたとして損害賠償を請求してくる場合もあります。この場合,法的措置に進む前に,労働者と交渉して,貴社の望む結果が得られるようにします。
参考裁判例
6ケ月以前の退職願の届出・会社の許可を必要とする旨の就業規則の効力よりも民法627条の適用が優先された例
高野メリヤス事件
東京地判昭51.10.29労判264-35
(裁判所の判断)
裁判所は,「法は,労働者が労働契約から脱することを欲する場合にこれを制限する手段となりうるも のを極力排斥して労働者の解約の自由を保障しようとしているものとみられ,このような観点からみるときは,民法第627条の予告期間は,使用者のためにはこれを延長できないものと解するのが相当である。従って,変更された…規定 は,予告期間の点につき,民法第627条に抵触しない範囲でのみ有効だと解すべく,その限りでは,同条項は合理的なものとして,個々の労働者の同意の有無にかかわらず,適用を妨げられない」と判示した。